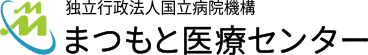診療内容
当センターの腎臓内科では、腎臓に関する病気の診療に当たっています。
ただし、腎臓癌などの腎臓腫瘍は泌尿器科の担当になります。
腎臓は、腰上部の両側にあるそら豆のような形をした握り拳ぐらいの大きさの左右一対の臓器です。腎臓は血液をフィルターで濾し出すことによって、血液中の老廃物や余分な水分を尿として身体の外に出しています。
尿を作り出す最小単位をネフロンといい、左右100万個ずつ、計200万個あります。1個のネフロンは、血液を濾し出す血管のフィルターである糸球体、濾し出された原尿から必要なものを再吸収したり、不要なものを分泌したりする尿細管・集合管などから成り立っています。
糸球体に異常がおこると血尿や蛋白尿が出現します。尿細管・集合管に異常が起きると腎機能低下が出現します。
具体的な病気としては、自覚症状はあまりなく、健康診断の尿検査で血尿や蛋白尿がみられる慢性糸球体腎炎、たくさんの蛋白尿がでて身体がむくんでしまうネフローゼ症候群、急に腎機能が低下する急性腎不全、徐々に腎機能低下が進行する慢性腎不全、急速に腎機能低下が出現する急速進行性腎炎などの病気があります。
腎臓が原因のものを一次性、全身の病気(高血圧、心臓病、糖尿病、膠原病など)に伴い腎臓にも病気がでてくるものを二次性といいます。
慢性糸球体腎炎は、放置しておくと約4割の方が20年前後で末期慢性腎不全になり、救命のためには腎代替療法(透析もしくは腎移植)が必要になります。進行するかどうか・治療をどうするかは、腎生検(約1週間の入院)といって、腎臓に針を刺して腎組織の一部を採取し、それを顕微鏡で観察する検査を行い、判断します。
残念ながら、進行性の慢性腎不全になった場合は、透析や腎移植の準備と開始が必要です。当院では、血液透析の治療を行っています。血液透析をするためには、内シャントといって、血液をたくさん取り出すことができるように動脈と静脈を結ぶ手術が必要です。当院では、内シャント手術、血液透析治療をしています。通常、血液透析を行えば、末期慢性腎不全の方も元気になり、週3回の通院治療をしています。
持続的携行式腹膜透析(CAPD)や腎移植を希望される方は、信州大学医学部附属病院腎臓内科に紹介しています。
その他、各種特殊疾患に関する血液浄化療法も行っています(診療実績参照)。
診療実績(令和3年度)
| 慢性腎臓病 | 11人 |
|---|---|
| 慢性腎炎症候群 | 4人 |
| 急性腎不全 | 4人 |
| 電解質及び酸塩基平衡障害 | 2人 |
| ネフローゼ症候群 | 1人 |
診療体制
常勤医師2名、非常勤医師1名体制で診療を行っています。
外来診療は、月曜日、火曜日は午前、午後、水曜日は午前、木曜日は午後、金曜日は午前となっています。
現状と今後の展望
2015年7月からエコー下経皮的腎生検を開始しました。2014年7月から月水金午後の血液透析を開始しました。2015年7月からは火木土午後の血液透析も開始しました。2015年4月に日本腎臓学会研修施設に認定されました。2015年12月に日本透析医学会教育関連施設に認定されました(信州大学医学部附属病院が教育施設)。
当院では持続的携行式腹膜透析(CAPD)、腎移植を除く腎臓病のすべての診療が可能です。スタッフ教育を行い、将来的にはCAPDの診療体制確立も検討中です。南松本・塩尻地域の腎臓病の診療に邁進するとともに、若手の腎臓内科医の研修施設として、また将来的には、信大病院に次ぐ中信地区の腎臓病の基幹病院となれるよう努力したいと思っています。